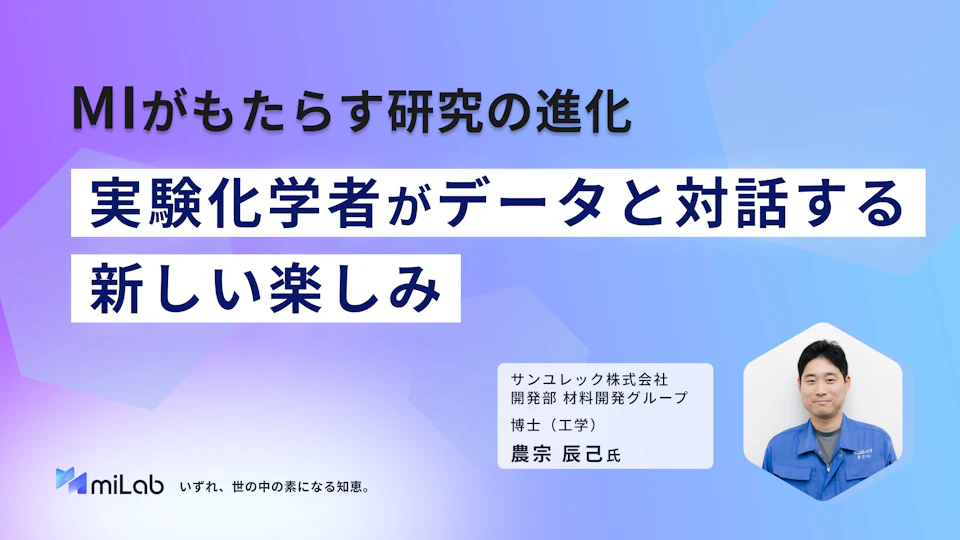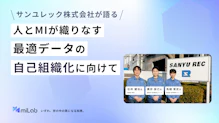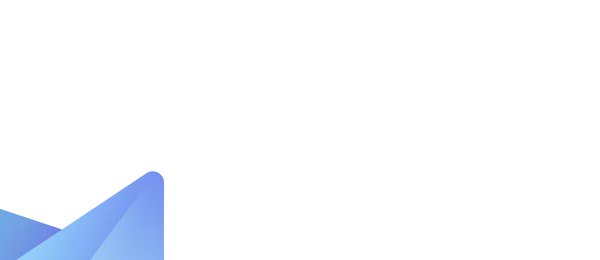はじめに―自己紹介とMIとの出会い
はじめに
マテリアルズ・インフォマティクス(MI)は、材料開発の課題解決を加速するキーテクノロジーとして注目され、多くの企業で導入や組織定着が進められています。研究DXやAI技術の進展も追い風となり、MIを取り巻く環境は急速に整いつつあります。近年は、MIの推進体制や導入事例に関する情報も多く見られるようになりました。
一方で、MIを活用する立場にある実験を主とする化学研究者(以下、実験化学者)の現場での実感は、まだ十分に共有されていないのが現状です。私自身、MIの推進者として組織内での定着を目指す一方で、実験現場でもMIを活用してきた立場にあります。
本稿では、そうした二つの立場から得られた経験をもとに、MIの魅力、導入時の苦労、そして今後への期待についてお伝えしたいと思います。
自己紹介
私は現在、MI推進者として組織定着の支援や教育活動を行うと同時に、実験化学者としてMIを活用した材料開発にも取り組んでいます。主な業務は、製品開発部門へのMIの実践支援・管理、社内教育の企画・実施、そして新技術・コア技術の研究開発です。
MIの取り組みは、当初は上司と二人三脚で始まりましたが、活用事例の共有や社内教育を通じて、徐々に仲間が増えてきました。数年にわたる取り組みの中で、MIの奥深さと有用性に日々驚かされながら、組織にとってMIが普遍的な技術となることを目指して活動を続けています。
MIとの出会い
数年前、社会人ドクターとして大学に在学中、AI技術やMBR(材料モデルベース研究; Model Based Research)(https://mmbr.hiroshima-u.ac.jp/)の概念を学ぶ機会があり、その中でMIに出会いました。
当時、コンピューターの飛躍的な進歩により、一般的なPCでもシミュレーションモデルの実装が可能になっていたことに加え、ニューラルネットワークを用いた深層学習(ディープラーニング)が注目を集めていました。深層学習の出現により起きた、人の「経験」や「勘」に近い複雑なモデルを構築できるという技術のブレイクスルーに、私は大きな衝撃を受けました。
さらにMBRでは、こうした技術を組み合わせ、最終製品の目標から逆算して材料を設計するというアプローチ(バックキャスト思考)が実行されており、MIが掲げる「理論と計算が主導する材料開発の未来像」を強く意識させられました。

図1. MBRの開発プロセス(理論と計算が導く材料開発の未来像)
出所:著者にて作成
講義を受けた後、「これからの材料開発では、理論・計算・実験の融合が不可欠になる」「やらなければ世界に取り残される」――そんな強い使命感に駆られ、すぐに上司にMIの必要性を提案しました。「近い将来、MIによりバックキャスト思考が材料開発の共通思想となり、開発スピードはMIで格段に加速していく。MIを早期に使いこなすことが必要です」と。この決断が、私のMIとの本格的な関わりの始まりでした。
本稿で伝えたいこと
こうして始まったMIへの挑戦は、決して平坦な道ではありませんでした。使命感を胸に取り組み始めたものの、現実には多くの壁がありました。しかし、その過程で見えてきたのは、MIの難しさと同時に、実験化学者だからこそ感じられる面白さです。MI推進者でありながら、実験とデータ解析を並行して進めるのは容易ではありません。それでも、両方の視点を経験したことで、研究の幅が広がり、これまでにない発想やアプローチを得ることができました。この経験を通じて感じたMIの魅力や可能性を、ここで共有したいと思います。
本稿が、MIに興味を持つきっかけや、挑戦を考えている研究者・エンジニアの一歩を後押しできれば幸いです。
MIで広がる研究の可能性 ― 実験と理論をつなぐデータ対話
活用で実感したMIの魅力
実験化学者の視点で私が感じるMIの魅力は、データとモデルを通じて“自分の分身”を育て、対話するような感覚にあります。仮説を立て、データをモデルに渡すと、思いがけない答えが返ってくる。その答えを考察し、新たな仮説を立て、データを追加し、条件を調整する――こうしたやり取りを重ねるうちに、モデルは次第に自分の研究スタイルを映し出す存在になっていきます。
MIで多く用いられる機械学習やディープラーニングなどのモデルは、統計的な帰納法に基づく手法です。日々、実験を通じて事象の解明を行う実験化学者の思考と親和性が高く、納得感を得やすいと感じています。
このようにモデルとの対話を重ねる中で、次第に自分の思考や経験が反映されるようになり、そこから得られる気づきが研究に新たな視点をもたらしてくれます。

図2. 実験と理論をつなぐデータ対話のサイクル図
出所:著者にて作成
データ対話から導く「経験」と「勘」の言語化
例えば、機械学習モデルから重要因子を解析したとき、自分の経験や勘と照らし合わせると、これまで言語化できていなかった抽象的な概念が具体化されることがあります。また、自分の経験と勘で立てた仮説に潜むバイアスが見えてくることもあります。これは、実験だけでは得られない新しい気づきです。
さらに、モデルから逆計算で最適条件を提案させるアプローチでは、自分が立てた実験計画と比較することで、計画の漏れや、思いもよらないユニークなアプローチを発見できます。実験の回数や時間には限りがあるため、こうした提案は非常に価値があります。特に、リスクを感じて躊躇しがちな条件に対して、MIが理論や計算化学の観点から「やってみる価値がある」と後押ししてくれるのは、孤独な研究者にとって心強いものです。
成長するモデル ― データ対話型研究の未来
MIの面白さをさらに感じるのは、逐次的最適化を用いたときです。実験サイクルを重ね、教師データが増えるたびに予測精度が高まっていく様子は、人が経験を積んで成長する姿に似ています。最初は、新人の部下にテーマを渡したときのように、失敗や見当違いが多い。しかし、検討の中期になると、中堅研究者のような思考を見せ、計算結果に納得感が出てきます。最終的には、テーマのパラメータ調整も重要ですが、ベテラン研究者の考えと一致する結果も多くなり、高度な対話ができるようになるのです。
AIとはよく言ったもので、データ(経験)を積み重ねて成長していく姿は、人材育成そのものです。違うのは、パラメータ調整という“指導”を加えることで、モデルは急速に成長するという点。世間では生成AI(特に大規模言語モデル:LLM)との対話が注目されていますが、実験化学者にとっては、MIとの対話研究が今後当たり前になるのではないか――私はそう期待しています。

図3. ヒトと成長モデルの対比
出所:著者にて作成
MI導入と推進のリアル ― 試行錯誤と仲間づくり
手探りから始まった導入プロセス
MIを研究業務に取り入れると決めた当初は、何が最適かもわからず、相談相手もいない状況からのスタートでした。プログラミング、AI、統計学、機械学習、逐次最適化などを学び、調べては実践を繰り返す日々。その中で痛感したのは、研究テーマに合った手法を見つける難しさです。モデルの精度が高くても、構築コストが大きい場合や有用な知見が得られない場合は、研究サイクルには合いません。 MIは単なるツールではなく、学問としての理解とノウハウが必要だと実感しました。
一方で、使い方次第で差別化できるのもMIの魅力です。私は学生時代、バイオマテリアルという複合分野を専攻していました。素材開発と医療が融合するその分野と同様に、MIも計算化学・理論化学・実験化学の融合領域です。だからこそ、推進することで新しい知見が生まれるのは必然だと、今では確信しています。
今はノーコードで始められる―小さな一歩から始まる実践
MI導入は一見難しそうに思えるかもしれませんが、現在では成功事例や便利なツールも増え、LLMを活用すればノーコードで簡単に機械学習も試せる時代です。私自身の最初の一歩は、Pythonで相関係数を計算したことでした。要因が不明な事象を分析する目的で実施し、担当者が仮説として挙げていた項目のスコアが高いことが確認できました。問題解決には至りませんでしたが、仮説が的外れではないことを裏付ける結果となり、研究の方向性を支える材料として意義がありました。
高度なアルゴリズムを使わなくても、表計算ソフトでデータを整理し、簡単な回帰モデルを作るだけでも立派なMIです。まずは身近な研究課題から試してみることが重要です。小さな成功体験の積み重ねが、MI推進の鍵だと考えています。
データ対話の実感が組織定着への鍵
MIを組織に定着させるためには、理解者を増やし、仲間の輪を広げることが不可欠です。私はイノベータ理論を意識し、自らがイノベータとしてスモールスタートで実績を積み、それを社内で広報することで仲間づくりに取り組んできました。

図4. イノベータ理論
出所:著者にて作成
当初は、言葉だけでMIの必要性を伝えても、周囲の理解は得られませんでした。しかし、実際にMIを活用し、成果を共有することで、徐々に関心を持つ人が増えていきました。特に、解析結果を発表し、議論する場を設けることが最も効果的でした。このように、実践を通じて得られた知見を共有することで、MIは“使える技術”として認識されるようになりました。
MIの有効性は、理屈で説明するよりも、実際にデータとの対話を体験してもらうことで強く伝わります。実験化学者の思考とMIのアプローチが一致していることを実感してもらえれば、納得感は格段に高まります。こうした体験を通じて、MIは単なる新技術ではなく、研究現場に根付く“共通言語”としての役割を果たすようになります。
このように、データとの対話を通じた実感こそが、MIの組織定着を促す鍵であり、技術の理解を超えて、文化として根付かせるための重要なステップだと考えています。
未来への期待 ― MIが拓く研究とコミュニケーションの新しいかたち
MIへの取り組みがもたらしたもの
MI推進を進める中で、着実にサポーターや仲間は増えてきました。私は社内勉強会や広報活動を通じて、MIの価値も共有してきました。その結果、開発実績だけでなく、研究者間でのコミュニケーションが活発になり、新しいコミュニティが生まれたことも大きな成果だと感じています。

図5. MIを共通言語とした新しいコニュニティの相関図
出所:著者にて作成
MI推進者としては、さまざまな研究テーマを支援でき、自分の専門領域を超えて幅広い素材開発に関われることを楽しんでいます。一方、実験化学者としては、データと対話するようになってから、アイデアの着想や考察、課題解決のアプローチが以前よりも豊かになったと実感しています。
未来への期待
素材開発において、MIは間違いなく強力な武器です。LLMの活用が急速に広がっているように、MIも近い将来、素材開発の現場で当たり前の存在になっていきます。特に、属人化が強いと言われる日本の研究開発において、MIによる「データとの対話」は、業界全体の発展に寄与し、研究者同士の新しいコミュニケーションツールとしての役割も果たすと期待しています。
さいごに
MIは単なる技術ではなく、研究の進め方そのものを変える可能性を秘めています。今後、理論・計算・実験がより密接に結びつき、研究のスピードと質が飛躍的に向上する未来を、私は楽しみにしています。そして、本稿がその一歩となり、皆さんとともにMIを通じて新しい研究の未来を築いていけることを願っています。