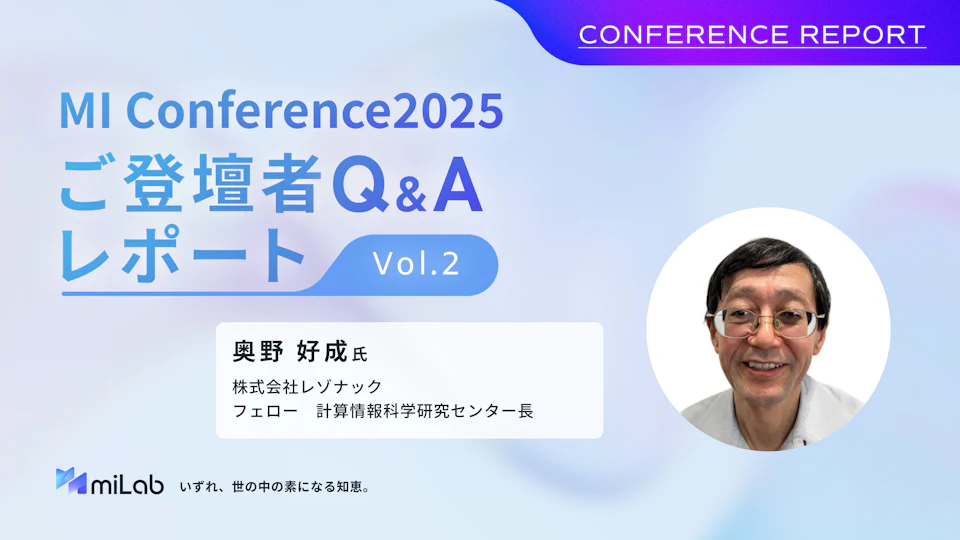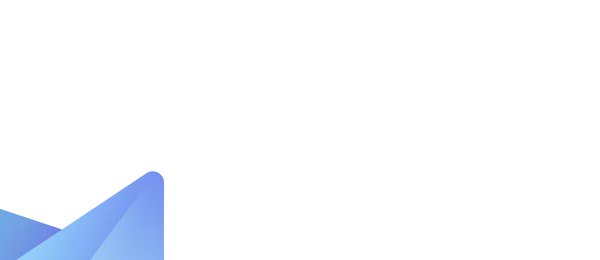近年、研究開発DXの導入・推進はますます加速し、単なる試験的導入を超え、組織レベルでの定着と拡張 にシフトしています。マテリアルズ・インフォマティクス(MI)やデータ活用を起点とした変革の波は、企業・アカデミアを横断しながら広がりを見せており、業界全体の競争力を左右する要素となりつつあります。
MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催し、過去最多となる1,800名以上の方々にお申し込みいただきました。
株式会社レゾナック 奥野氏のご講演では、「レゾナックにおけるMIの組織活用・推進」をテーマに、MI活用の具体的事例と共に、データパイプライン(MI活用のための構造化データの蓄積を行う仕組み)や、アプリ・ソフトの現場展開について、詳細にご説明いただきました。
本記事では、参加者の方から積極的に頂いた多数のご質問に対して、奥野氏から開催後にご回答いただいた内容をご紹介いたします。

奥野 好成
Yoshishige Okuno
株式会社レゾナックフェロー 計算情報科学研究センター長
慶應義塾大学 理工学部化学科 卒業
慶應義塾大学 大学院 理工学研究科化学専攻 修士課程修了
化学メーカー就職
京都大学工学博士(論文提出による)
独立行政法人、ソフトウェア会社勤務を経て、 昭和電工株式会社 研究開発本部研究開発センター計算科学グループリーダー、事業開発センター計算科学・情報センター長、理事 融合製品開発研究所 計算科学・情報センター長、株式会社レゾナック理事 計算情報科学研究センター長を経てフェロー計算情報科学研究センター長、現在に至る
組織体制・人材育成に関して
貴センターが若手チーム(平均年齢30歳)で構成されていることに感銘を受けました。世代の異なるメンバーを束ねる中で、成果最大化のためのコミュニケーションや信頼関係構築において工夫されていることがあればぜひ伺いたいです。また若手の自律性や創造性を引き出すための組織づくりについても、お考えをお聞かせいただけますと幸いです。
徐々に採用を増やしてきまして、特に優秀な学生さんを確保することに注力してきた結果、若手が多い部署になっています。コミュニケーションに関しては1on1やラウンドテーブル等で若手の皆さんの意見を聞く努力をしています。若手の自律性や創造性を引き出すため、少し挑戦的なテーマを決めて、それをやり遂げていただくような研修テーマを設定しています。
データサイエンスとアプリ開発・運用はまた異なる専門性があるかと思いますが、チーム内にデータサイエンティストとWebエンジニアがいらっしゃるのでしょうか。それともデータサイエンティストがアプリ側の知識も身につけているのでしょうか。
それなりの人数規模になってきたため、センター内にいろんな分野の人がいるようになってきました。計算科学・情報科学・IT基盤構築のそれぞれの専門家が役割分担をする場合もありますし、お互いに相談しながら一人でアプリ開発・運用まで行う場合もあります。ケースバイケースで進めてきましたが、徐々に役割分担することが多くなってきました。
社内でデータサイエンティストの認定制度を導入されたとのお話でしたが、ユーザーのモチベーション向上に繋がったのでしょうか。それとも、資格手当など他のインセンティブも与えているのでしょうか。ユーザーの反響について教えてください。
社外の資格に関しては費用負担の補助がありますが、社内のデータサイエンティスト認定に関して資格手当はありません。認定されたということがモチベーションとなっています。
MI導入により、研究者の働き方や思考プロセスに変化はありましたか? 具体的にどのような変化があったか興味があります。
MIに対する見方は、研究者それぞれではありますが、徐々に、MIを導入しないと時代に遅れているという思考になりつつあると思います。特にMIを使うことでうまくいった事例が増えてくるにつれて、周りも影響されてというところがあります。また、MIや計算での開発は、顧客にも、なぜ弊社の製品がいいのかの説得材料になり、他社品と同程度の特性であれば、良い特性が出る理由がはっきりしている弊社の製品が採用される確率が高くなるように実感しています。
データサイエンス、MIに関して
貴社のように多岐にわたる事業セグメント(半導体・電子材料、モビリティ、イノベーション材料など)を持つ中で、MIの戦略や重点分野はどのように決定され、各セグメントへ展開されているのでしょうか?
元々、旧昭和電工が計算情報科学に強かったために、旧昭和電工で主にやっていた、電子材料・イノベーション材料に活用していたのですが、現在は、半導体材料に重点を移しております。これは、レゾナックの全社方針として、成長分野である半導体材料に注力することになったからです。
ポリマーと混合溶媒の相溶性を予測するにあたり、すべてがスムーズに完了できたのでしょうか?なにか課題等はあったのでしょうか?
試行錯誤は数多くありました。特に、実験研究者の暗黙知には悩まされてきましたし、今でもそれが大きな課題です。いろんな理由で使ってはいけない溶媒やモノマーが存在する等ですね。ただ、そこは一つ一つ、個別の分野の勉強をしながら進めていくしかないと思います。分かってきますと、似たようなテーマであれば、こちらも暗黙知が分かってきますので、最初1年かかっていた案件も、2回目は半年、3回目は3か月といった風に、加速度的に各テーマに対応できるようになってきました。
データ基盤・データ管理・アプリに関して
データパイプラインを構築する上で、最も苦労された点はどのようなことでしたか? 例えば、データの品質管理、異なるデータ形式の統合、従来データの取り扱いなど、具体的な課題とその解決策を教えてください。
異なるデータ形式の統一が一番難しい課題でしたし、その課題は今でもあります。使いやすい形式が研究者個人によって異なるため統一した形式で合意をとるのが大変でした。ただ、慣れの問題でもあり、一旦、グループ単位で形式を決めてしまえば、その形式で書くことへの違和感は徐々になくなっていくようです。
データベース構築は各部署独自のものではなく、全社で共通のものを使用しているのでしょうか?
各テーマ別でデータベースを構築していて、全社統一したものではありません。テーマ毎に必要とされるデータは異なることから、全社統一のデータベースは構築していませんし、統一するメリットはないと判断しています。
構造化データに自動で整形してくれるシステムはどのような仕組みでしょうか。生成AIなどでしょうか。
Pythonで作成したプログラムになります。最近は、生成AIでもプログラムを作成できるようになっていますので、近い将来、生成AIに自動整形を任せることができるのではないかと期待しています。
将来的に、ウェブアプリや統計解析ソフトを、どのように進化させていきたいとお考えでしょうか? AIとの連携や自動化など、展望があればお聞かせください。
実験データが少ない課題を克服するため、物理法則に基づくシミュレーションでデータを蓄積し、それによるデータ解析を活用する方向に進めていこうと思っています。シミュレーションデータと実験データの違いは、転移学習等を用いて対応することができ、それによって、実験データが少なくても、シミュレーションで補うことで、外挿予測に強いAIモデルができると思います。
電子実験ノート (ELN)に関して
電子実験ノートの機能追加において一番利用者増につながった機能は何ですか?
個々の研究者のニーズが異なるため、何か一つの機能で利用者増につながったわけではなく、いろんな機能を付与して、その機能に魅力を感じてくれた方々が徐々に使うようになっていただいたと思います。ただ、最近では生成AIの進歩のおかげで、文書を共有できる場所に残しておくことの重要さが認識されつつあり、電子実験ノートに関する印象が変わりつつあると思います。
電子実験ノートはサブスクであり、毎年数百人の研究員が使用するとなるとそれだけの費用が毎年掛かるかと思いますが、導入に際し費用に関してはどのように考え導入されましたでしょうか?
トータルしますと確かに結構な金額ですが、一人当たりで考えますと、特に高額なわけではありません。普段、我々が使っているパソコンやオフィスのソフトやITインフラと同じで、研究開発を進める上で必須と考えて導入しています。それによって、新ヒット製品の開発に1つでもつながれば、十分、元が取れるという考え方です。
電子実験ノートの導入には多方面との整合が必要かと思うのですが、レゾナック様で電子実験ノートを普及された際には、どの部門、役職などから普及されていきましたでしょうか。
元々、製薬メーカー向けで作られた電子実験ノートですので、それに近い分野の化学物質を扱う研究開発部門から導入しましたが、それ以外の分野でも使えることが分かってきましたので、研究開発のいろんな部門に導入いただいています。一方で、情報共有がメリットですので、一人や二人が導入してもメリットがないため、グループ単位(リーダーを含めて10人程度以上)で導入していただいています。グループで電子実験ノートに書くということを決めていただければ、皆さん、電子実験ノートに書く習慣ができると思います。
皆様、いかがでしたでしょうか。
奥野氏の講演本編では、「レゾナックにおけるMIの組織活用・推進」をテーマに、MI活用の具体的事例と共に、データパイプライン(MI活用のための構造化データの蓄積を行う仕組み)や、アプリ・ソフトウェアの現場展開についてもお話いただきました。
ご講演の概要記事についても、ぜひご覧ください。