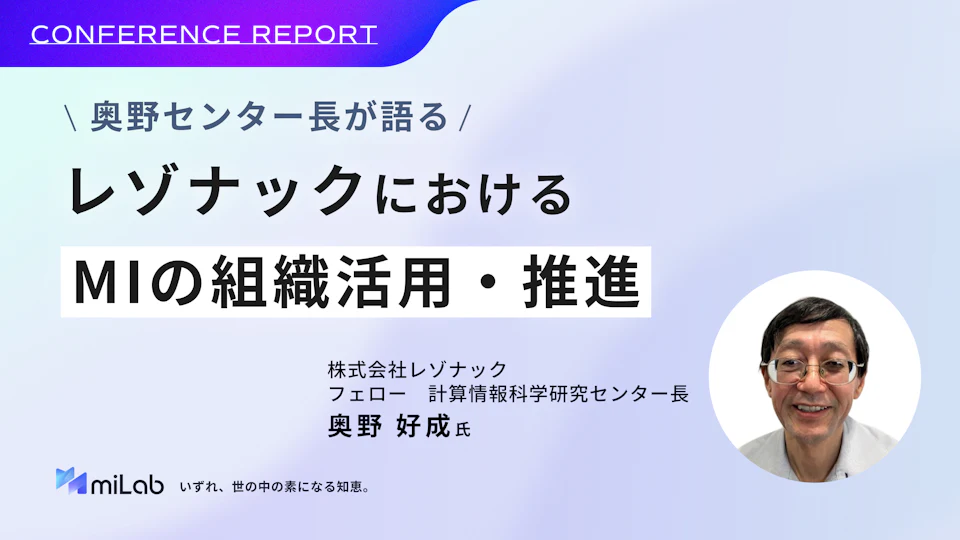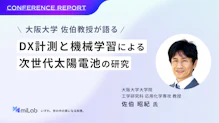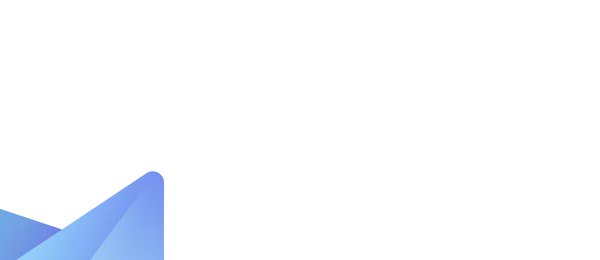MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催いたしました。
本記事では、株式会社レゾナック 奥野氏の講演内容の一部を抜粋してご紹介いたします。

奥野 好成
Yoshishige Okuno
株式会社レゾナックフェロー 計算情報科学研究センター長
慶應義塾大学 理工学部化学科 卒業
慶應義塾大学 大学院 理工学研究科化学専攻 修士課程修了
化学メーカー就職
京都大学工学博士(論文提出による)
独立行政法人、ソフトウェア会社勤務を経て、 昭和電工株式会社 研究開発本部研究開発センター計算科学グループリーダー、事業開発センター計算科学・情報センター長、理事 融合製品開発研究所 計算科学・情報センター長、株式会社レゾナック理事 計算情報科学研究センター長を経てフェロー計算情報科学研究センター長、現在に至る
ご講演の紹介
株式会社レゾナック(以下、レゾナック)は、半導体・電子材料、モビリティ、イノベーション材料、ケミカルといった多様な事業セグメントを展開し、世界トップクラスのシェアを誇る製品を多数有する機能性化学メーカーです。
MI Conf 2025では、同社の計算情報科学研究センター長として研究開発DXを牽引してこられた奥野氏から、MIの活用事例や構造化データの蓄積など、豊富なご経験を元にご講演いただきました。
はじめに
レゾナックは、2024年FY連結売上高約1兆3,893億円、営業利益787億円を誇る大手化学メーカーです。半導体・電子材料、モビリティ、イノベーション材料、ケミカルなど多岐にわたる事業を展開しており、特に半導体前工程材料のガス製品や研磨材料、リチウムイオン電池材料、半導体後工程材料などが主要なセグメントです。
同社のMI推進を担うのは、横浜とつくばに拠点を置く「計算情報科学研究センター」です。平均年齢約30歳の若手中心の90名が所属し、計算科学技術と情報科学技術の両方をフルラインで保有している点が特徴です。原子・分子レベルのミクロシミュレーションから、マクロシミュレーション、AI/MI、さらにはIT基盤構築まで、あらゆるデジタル技術を駆使し、多様なテーマの課題解決を通じて研究開発の加速に貢献しています。
マテリアルズインフォマティクス(MI)活用事例
レゾナックでは、約10年前、まだAIが一般的に認知されていない時期から、国のプロジェクトへの参画を通じてMI技術の確立と実用化を進めてきました。特にポリマーや複合材料の開発において、MIが大きな威力を発揮しています。
ポリマー特性解析:独自のディスクリプター開発と機械学習予測
ポリマーのような複雑な化学構造をコンピュータで扱うには、数値データへの変換が不可欠です。レゾナックは、既存のExtended Connectivity Circular Fingerprint (ECFP)を基に、ポリマーの特性予測に最適化した「数密度ECFP」という独自の数値ディスクリプターを開発しました。これを活用し、次元削減(LASSO回帰)やガウス過程回帰などの機械学習手法を組み合わせることで、高精度な予測モデルを構築しています。
例えば、51種類のポリマーの屈折率予測において、従来のDFT(密度汎関数理論)計算で53時間かかる予測を、機械学習を用いてわずか0.25秒に短縮することができました。この圧倒的な計算速度のメリットは、さらに多くの材料の探索・設計を可能にします。
ベイズ最適化による効率的な材料探索
ベイズ最適化の概念を導入することで、材料探索の効率化を実現しています。従来、無作為なポリマー探索ではターゲットポリマーの発見に約192回の試行を要しましたが、ベイズ最適化を活用することで、平均4.6回の試行でターゲットポリマーの発見に成功し、試行回数を約1/42に低減できました。これは、少数のデータからでも効率的に最適な材料を探索できることを示しています。
熱硬化性樹脂のAI解析と実践的な成果
実際に熱硬化性樹脂のポリウレタンフィルム開発では、AI解析モデルの構築により、原料ジオールモノマーの構造とモル比、プレポリマーの水酸基価を説明変数とし、屈折率、破断応力、伸びを目的変数として同時最適化を試みました。その結果、27点の教師データからAIが提案したわずか3点の組成の実証実験で、既存の実験を上回る樹脂性能を達成し、試行回数を少なくとも1/25削減することに成功しました。
量子インスパイアード技術の活用検討
レゾナックは、さらなる最適化の高速化を目指し、量子インスパイアード技術も活用しています。
- 混合溶媒の最適化: 複数の溶媒を混合し、最適な溶解度パラメーター(HSP値)とコストのバランスを持つ組成を見つける課題に、量子現象に着想を得たコンピューティング技術を応用しました。多数の溶媒組み合わせにおいて、デジタルアニーラを用いることで、従来の網羅計算(5種溶媒で約40年と概算)と比較して、8.9分での高速な最適値計算を実現しています。
- 機械学習解析モデルの高速最適化: 複合材料の最適な特性を見つけるための機械学習モデルの最適化にも、この技術が適用されました。学習データからFactorization Machineを用いた解析モデルを構築し、その最適化問題をイジングモデルに変換してデジタルアニーラで解きました。全数探索で809時間かかる計算を58秒に短縮し、約49,895倍の高速化を達成しました。
これらの量子インスパイアード技術を応用し構築したシミュレーテッドアニーリング技術は、既にレジスト開発に応用され、レジスト用ポリマーの最適組成の探索期間を従来の1/5に短縮するなどの成果を出しています。
データパイプライン:構造化データの蓄積を行う仕組み
MIを最大限に活用するためには、質の高いデータの蓄積が不可欠です。レゾナックは、実験データの効率的な収集と構造化のため、電子実験ノート(ELN)の導入とデータパイプラインの構築を進めています。
2019年頃からELNの導入を開始した後、利便性の高い機能追加や社内での情報共有の促進により、2024年にはライセンス数が1,000以上に増加し、全研究員の1/3以上が利用しています。
このELNは、実験現場で生成される合成・測定条件や結果などの多様な情報を、決まったフォーマットで記録・アップロードする仕組みを提供します。データパイプラインは、ELNに登録されたデータを自動的に整形し、コンピュータが読みやすい構造化データとしてデータベースに蓄積します。これにより、研究者と解析者の手間を削減し、解析サイクルの高速化を実現しています。万一、データ入力に誤りがあっても、解析結果からELNへ簡単に戻って確認・修正できるトレーサビリティも確保されています。
ウェブアプリや統計解析ソフトの活用
さらに、専門性の高いAI解析モデルを誰もが利用できるよう、ウェブアプリケーション化を進めています。ポリマーAI予測システムや合金AI予測システム、品質管理AIウェブアプリなど、30以上のAIウェブアプリが開発され、クラウドサーバーにデプロイされています。これにより、材料開発者はデータサイエンスの深い知識がなくとも、分子構造の入力から物性予測や評価を容易に行うことが可能です。ウェブアプリ形式は、バージョンアップが容易で、現場の知見を活かしたAI結果の解釈を促し、「人とAIの共創」を推進しています。
また、統計解析ソフトの全社的な普及活動も積極的に展開しています。
この支援のため、新入社員研修や、統計知識と活用能力を評価する社内「データサイエンティスト認定制度」(ブロンズ級、シルバー級、ゴールド級)を設け、データリテラシーの向上と製品開発効率の向上を図っています。これにより、データサイエンティストの負担軽減と、現場の材料専門家による自律的なデータ活用を促進しています。
まとめ
MI活用事例では、独自の機械学習モデルの構築や、最先端のコンピューティング技術を活用し、多数の成果を挙げています。
また、データパイプラインの取り組み・ウェブアプリや統計解析ソフトの活用では、「人とAIの共創」を目指し、既に1,000人以上のユーザーが活用する体制を確立しているとお話しいただきました。
皆様、いかがでしたでしょうか。
Q&A記事では更に、当日頂いた多数の質問にご回答頂いています。ぜひこちらもご覧ください。
miLab編集部からのメッセージ
奥野氏のご講演は、レゾナックにおけるMI活用を「研究テーマへの適用」から「組織全体への展開」までカバーくださいました。特に、ポリマー開発での飛躍的効率化の事例や組織的なアプリケーションの普及は、産業界にとって貴重な先行事例です。また、若手研究者が中心となる計算情報科学研究センターの存在は一際目立っており、その点に関する質問の多さが印象的でした。
奥野氏に改めて感謝申し上げるとともに、本記事が読者の皆さまにとって、自組織におけるMI推進の参考となれば幸いです。