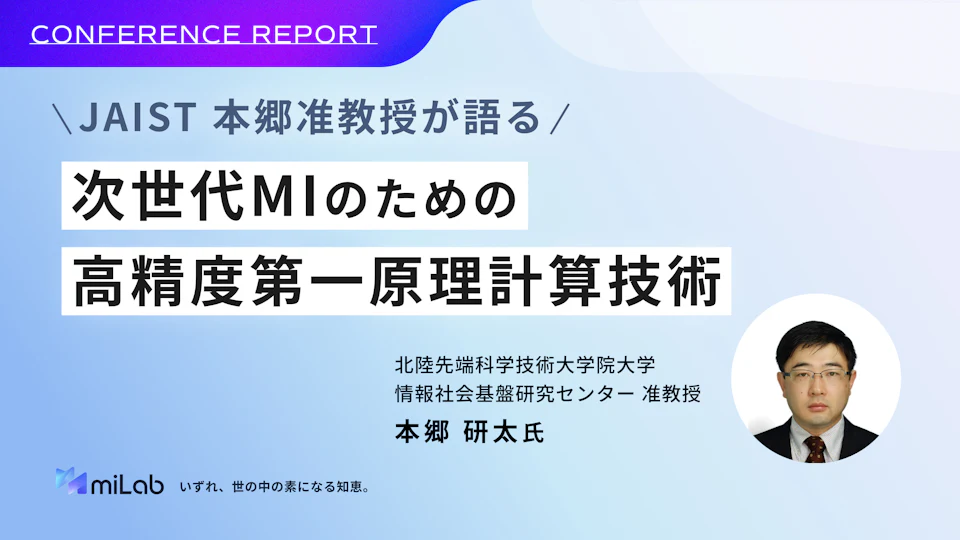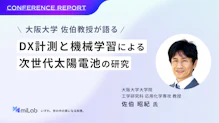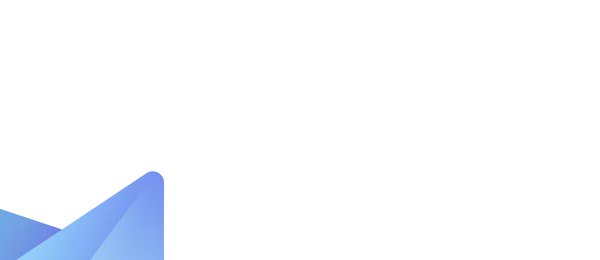MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクスに特化したカンファレンス「MI Conference 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催いたしました。
本記事では、MIConf2025より、北陸先端科学技術大学院大学 本郷氏の講演内容の一部を抜粋してご紹介いたします。
北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)情報社会基盤研究センターの准教授である本郷研太氏により、アカデミアから見たマテリアルズインフォマティクス(MI)研究の現状と、その方法論の展開について、先生ご自身の研究事例を交えながら、第一原理計算データと生成AIの融合によるMIへの取り組みを紹介いただきました。

本郷 研太
Kenta Hongo
北陸先端科学技術大学院大学情報社会基盤研究センター 准教授
2005年に東北大学大学院工学研究科で博士(工学)を取得した後、東北大学金属材料研究所、北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、ハーバード大学(海外学振)、統計数理研究所を経て、2012年にJAIST情報科学研究科の助教として着任、2017年には准教授へ昇進し、情報社会基盤研究センターにてスーパーコンピュータ施設の管理も担当している。研究分野は第一原理量子モンテカルロ法を活用した計算材料科学およびマテリアルズ・インフォマティクスに従事している。物質科学における基礎研究のみならず、企業との産学連携研究にも従事している。
統計科学と物質科学の融合:マテリアルズインフォマティクス(MI)
MIの適用対象は無機化合物から有機化合物、生体分子まで多岐にわたり、第一原理計算や分子動力学計算、計算熱力学といった多様なシミュレーション手法が用いられています。さらに、AIの進展を活用した材料研究もMIの中核をなしています。MIにおける主要な課題は、新物質探索であり、これは大きく二つの問題に分けられます。
- 順問題: 化合物の構造が与えられたときに、その物性を予測する。これは物質科学シミュレーションや機械学習で解決可能です。
- 逆問題: 特定の物性を持つ化合物を探索する。これは機械学習やAIを用いて行われます。
しかし、化合物空間は非常に広大で、1060個もの化合物が存在すると推定されています。これに対し、現在知られている化合物はわずか1010程度に過ぎません。この広大な空間から目的の物質を効率的に見つけ出すことが、MIの重要なテーマとなっています。
生成AIとディープラーニングが牽引するMI研究の進化
MI研究の進展には、データの存在が不可欠です。物性予測においては、従来は記述子を設計して機械学習に適用していましたが、最近ではMaterials ProjectやOQMDのような大規模データセットを活用し、深層学習を用いて記述子の生成と物性予測を同時に行う手法が進展しています。
中でも特に注目されているのが、生成AIの物質科学分野への応用です。ChatGPTなどの大規模言語モデルで広く知られる生成AIが、MIにおいても活用され始めています。AI技術は、ディープラーニングによる画像認識から、チャットボットや画像生成といった生成AIへと進化し、最近では「拡散モデル」と呼ばれる新しい生成AIが登場しています。この拡散モデルを用いることで、分子構造やタンパク質のより複雑な構造を実際に生成することが可能になります。
MI分野の学術論文数は増加の一途をたどり、市場規模も拡大が予測されるなど、MIは基礎研究から実用的な段階へと移行しつつあります。本郷研究室でも、MI関連の共同研究が企業との間で5件ほど進行しており、その実用化への期待の高さが伺えます。
MIの課題と第一原理計算の重要性
MIの発展が進む一方で、課題も浮上しています。特に、情報科学や統計科学、そして材料科学の双方に精通した人材の不足が顕在化しています。また、機械学習の限界も指摘されています。機械学習は、既知のデータに基づいて物性を予測する(内挿的予測)においては高い精度を発揮しますが、生成AIによって生み出された未知の化合物など、データが存在しない領域の物性予測(外挿的予測)においては、その信頼性が保証されません。
この課題を克服するためには、「物質科学シミュレーションと機械学習を両輪で進めていくアプローチ」が重要であると考えています。
物質科学の基礎原理:第一原理計算
物質の性質は、その構成要素である原子核と電子の振る舞いによって決定されます。約100年前に確立された量子力学は、特に物質中の電子の振る舞いを記述する基本方程式として、シュレーディンガー方程式を定式化しました。この方程式が解ければ、どのような物質であっても、その性質を予測することが可能になります。
シュレーディンガー方程式は、電子の位置座標に関する関数を含む偏微分方程式であり、未知のエネルギー値と関数を求める「固有値問題」として解かれます。特に、原子の配置によって決まる「ポテンシャル」が分かれば、この方程式を解くことで物質の状態、ひいては電子のエネルギーを導き出すことができます。
シュレーディンガー方程式の厳密な解法は複雑ですが、適切な「当たり」をつけることで解の精度や信頼性が向上します。統計的なサンプリング手法を用いることで、高い信頼性を持つ計算も可能になります。
第一原理計算の解法と本郷研究室の研究事例
第一原理計算の解法には様々な流儀があり、電子のポテンシャルの取り扱い方によって異なります。現在デファクトスタンダードとなっているのは「密度汎関数理論(DFT)」です。その他には、化学分野で発展した「分子軌道法」や、統計的なサンプリングを用いて高精度に解く「量子モンテカルロ法(QMC法)」などがあります。
これまで、第一原理計算のための分子構造の準備は研究者が手作業で行っていましたが、AIによる構造生成が可能になったことで、ハイスループットな計算が実現しています。本郷研究室では、このような進展を活かして「結晶構造探索」の研究に取り組んでおり、以下のような成果が得られています。
- 高温超伝導体候補の理論探索:Y-Mg-H, Mg–Sc–H, La–Y–H 系などの水素化物について結晶構造探索を行い、高い超伝導転移温度が期待される候補構造を理論的に提示
- 高圧下の金属水素研究:惑星内部に相当する 400〜500 GPa の極高圧条件において新しい相構造の存在を予見し、その安定性や物性を検討
特に、金属水素のような非常に高い精度を要求する系では、通常のDFT法では精度が出にくいため、量子モンテカルロ法(QMC法)のような、より高度な方法が用いられます。
量子モンテカルロ法の強みと汎用性
QMC法は、金属水素のような高精度が要求される系だけでなく、生体分子や分子結晶といった「弱く結合している」系(分散力や分子間力)に対しても、高精度な計算が可能です。従来のDFT法では、DNAのスタッキングのような分子が結合している状態が、バラバラになった方が安定だと誤って予測されることがありましたが、QMC法はDNAがきちんと結合した状態を正確に再現することが可能です。
これまでの物性第一原理計算の中心はDFT法と分子軌道法でしたが、それぞれ取り扱えるサイズと結果の信頼性においてトレードオフがありました。一方、QMC法はこれら二つの手法の中間的な位置を占め、高い汎用性を持つことが特長です。近年、QMC法は実用性を増しており、産業応用やMIへの展開にも期待が寄せられています。
JAISTの産学連携の取り組み
JAISTは、設立当初から企業との共同研究に積極的に取り組んできました。スーパーコンピュータなどの計算資源を煩雑な申請や課金なしに利用できる体制を整えており、企業にとっても研究を進めやすい環境が整っています。
また、東京サテライトキャンパスでは社会人向け博士課程を開講。職場で扱うデータを研究テーマに活用できる仕組みを整え、最短1年で博士号を取得できる制度も用意されています。こうした柔軟な教育プログラムは、実務に直結する研究人材の育成と、企業ニーズに即した研究推進の両立につながっています。
まとめ
講演では、MIの最新動向と、その中核をなす第一原理計算技術の重要性について解説し、「機械学習とシミュレーション」の両輪アプローチに基づき、高性能なスーパーコンピュータを活用した具体的な研究事例を紹介しました。特に、一般的なDFT法では精度が難しい系に対して、高精度な量子モンテカルロ法(QMC)が有効であることが示され、その汎用性と産業応用が期待されます。
編集部からのメッセージ
本郷准教授のご講演は、第一原理計算とAIの融合がいかに新物質探索を加速しうるかを示してくれるものでした。機械学習とシミュレーションを「両輪」で組み合わせるという考えは、生成AI時代のMIにおいても欠かせない基盤だと感じます。
また、教育・研究環境面で先端研究を支えている点についても言及されたのが印象的でした。実際に、弊社のプロダクト開発マネージャーも社会人博士として本郷研究室に在籍し、現場の課題意識と学術的知見を往復させながら学びを深めています。
第一原理計算やAIを軸とした研究が産業界に根付くためには、こうした産学双方の往来と協働が欠かせません。編集部としても、今後もこうした取り組みを取り上げながら、研究と実務が相互に高め合う未来を一緒に盛り上げていきたいと考えています。