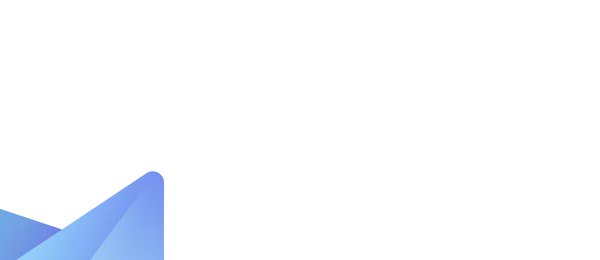MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催いたしました。
多くのセッションで参加者の方から積極的にご質問いただきました。
当日すべてに回答できなかったことから、本記事では、積水化学工業株式会社 新明氏から開催後にご回答いただいた内容をご紹介いたします。

新明 健一
Kenichi Shinmei
積水化学工業株式会社先進技術研究所 情報科学推進センター センター長 兼 MI推進グループ長
2008年に積水化学工業(株)に入社し、燃料電池、リチウムイオン二次電池の研究開発に従事。実験計画法、品質工学を導入し開発の加速を実践。2015年より2年間、アメリカのミズーリ大にて派遣研究員としてCO2資源化に関する触媒開発に従事した。帰国後は、触媒材料開発のハイスループット化、統計解析を材料探索に適用するなどMIの導入を先導した。2020年より情報科学推進センター MI推進グループのグループ長として、全社の開発・製造テーマへのMI活用を推進している。自らも10以上の開発・製造テーマと連携し開発加速、新材料提案等に貢献。2024年から現職として全社開発DXの推進を先導している。
MI推進と組織文化・人材育成に関して
MIの社内展開において、モチベーションの高いメンバーが主導するもそこから展開する際に普及が進まないという事例が見受けられます。データサイエンスになじみのない技術者や中堅層にMIを普及していく上で意識していることはありますか?
非常に重要な課題という認識です。MIをこれから普及する段階であれば、普及する当事者が危機感を持っており、進めなければならないと考えている部署から進めること、スモールでいいので成果創出までの道筋を、最初の段階で立てられるテーマを選定することが大事だと思います。
まずは、そういった開発テーマ、人、チームとの連携によって、成果を、小さくてもいいので創出すること。成功事例が出てくると、データサイエンスになじみのない技術者や中堅層も、だんだんと前向きに取り組んでくれるようになってくれるものと考えています。
上記のような危機感を持ち、前向きであって、ただ単にデータサイエンスになじみがないだけであれば、幸いに世の中にはデータサイエンスに関するセミナーや講座がありますので、社内に教育の仕組みが無い場合は、そういったものを活用するのも手だと思います。
弊社ではMI解析が一人のエース頼みになってしまい、その担当者の負荷が大きいこと、担当者が抜けた際にMI推進活動が止まってしまうことを懸念しています。人材育成、採用で工夫していることがあれば教えてください。
一人のエース頼みということであれば、やはり早々に後継の育成を進める算段を進めることが重要だと思います。人材育成は時間がかかるので、焦りすぎず、個々のメンバーを1年~2年スパンで見て、2年後にはこういう人材に成長させるというのを本人と握ることが重要だと思います。当部署では、スキルマップで定義されるMI人材レベルの目標を人事考課で設定し、到達度を半年ごとにモニタリングしています。また、特に、エース級候補に対しては、高度なテーママネジメントが必要なストレッチテーマをあえて与えて成長を促すような施策も実施しています。結局、人材育成は、打ち出の小槌のような魔法の方法は無く、地道に、かつ計画的に、そして着実に実施することが近道だと思います。
MI導入後、社内の組織体制や意思決定プロセスにどのような変化がありましたか? 円滑なMI活用を進めるための組織設計のポイントがあればぜひ教えてください。
開発部署によって、組織の大きさ、雰囲気、文化、人材がバラバラなので、ケースバイケースですが、個々の開発テーマというミクロな視点においては、例えば、事例で話した、フィルム製品の開発に関しては、意思決定プロセスが大きく変わりました。
具体的には、顧客要望があったときに、まずは我々が作った機械学習モデルにて、候補配合の提案と実験がおこなわれるようになったこと。また、MIによる新配合提案品の承認プロセスがデザインレビュー(DR)レベルで記載されるに至ったので、開発そのもののフローが変わりました。また、上記のような成果が出始めると、1つの開発テーマ単位ではなく、大きな組織単位(10近くの開発部署が傘下にいる組織)で、MIをベースとした新製品開発ができないかと検討を始めた組織も出始めています。
組織設計のポイントという観点では、組織体制や意思決定プロセスに変化のあった部署は、すべからく開発部署側の担当者が相当な危機感(これを進めないと未来は無い)や、絶対にMIを活用して開発を加速できる状態にしたいという強い想いを持っていました。そういった想いを持った方との連携状態を取りこぼさないことがポイントではないかと思います。
実験は失敗データも評価されますが、MIや計算は成功しないと評価されない点はどの様に克服されていますか。
成功しないと評価されない点を克服するというよりは、成功すること=開発や事業に貢献することを目標としています(成功して評価されるようにMI推進の仕組みを整えている)。
当日の発表でもお話ししましたが、当部署では、MIや計算を使って提案することがゴールではなく、開発加速、顧客採用、MI提案による新製品の上市による売上に繋がって、はじめて成功と定義しています。そのための指標も貢献KPIとして、半年ごとに可視化しています。また成功確度を上げるために、受託KPIという指標で、MI活用のテーマ選定も実施しています。
MI戦略と展開に関して
開発担当者自身の知識向上でMIツールを回せるようになってくると、将来的にはMIを推進するような部署はいらないように思うのですが、長期的なMI部署のビジョンはどのようにお考えでしょうか?
おっしゃる通り、個々の開発担当者が担当する開発への適用という観点では、将来的には、開発者自身がMIを推進する未来がそう遠くない形でやってくると認識しています。ただし、例えば、似たような材料を扱うけど、顧客ごとに開発担当者が分かれている場合のデータ連携(もちろん、連携されたデータを活用して、より精度の高い提案等)、開発データと計算データを融合しての高度なモデル化と材料提案など、個々の開発担当者では、なかなか対応できない領域(他にもここには記載しないが、個々の開発担当者では難しそうだなと思うことはたくさんある)が残るとも考えており、開発担当者が個々で進める領域、MIの専門部署と連携して進める領域というのが分かれていくのではないかと考えています。
初期の連携テーマは、「センター側からのアプローチ」、「事業部門からの依頼」「トップダウンによる取り組み」のどれによって推進されたのでしょうか?
主に、「センター側からのアプローチ」「事業部門からの依頼」です。
KPI設定や教育体制構築は、MI関連の開発を実施しながら並行で取り組まれたのでしょうか。それとも開発部隊と構想策定部隊とが分かれていたのでしょうか。また、MIに関する決定権を持ちながらどのようなステップで全社展開を行っていかれたか、可能な範囲でご教示いただけますと幸いです。
並行で進めました。開発とのテーマ連携を通して、テーマ担当者自ら(私も含め)が、KPIや教育体制の制度設計、試行、ブラッシュアップを繰り返しました。
初期検討段階ではついDB化は後回し、ファイルベースでのやり取りでとなってしまいがちかと思ったのですが、しっかり仕組みの中にDBの要素を入れられているところは何かこれまでの経験からの勘所なのでしょうか?
このテーマでのDB化は、大きな1つの完成されたシステムを構築したというよりかは、対象となる開発品の配合と品質にフォーカスされた簡易的なもの(その意味では、DBの要素は的を射た表現)でしたが、テーマの成否に与えた影響は大きかったです。
このテーマは私自身が担当したものでしたが、DBの要素を入れた理由としては、大きく2つあり、
① 自身の受けた教育。学生時代の先生が研究データを残すにあたって、非常に厳しい人で、すべてのデータをコード化して管理していましたが、逆に言うと、この方法でないと実験していないのと同じだと言われ続けてきました。思い返すと、コード化は、研究室のメンバーが同じルールで運用していたので、誰の実験でも、研究室メンバーであれば、データを簡単に参照できますし、数年前のデータも簡単に見つけられるので、まだにDB化の利点を、知っていたことが大きかったかと思います。
② 現場の負担軽減。本テーマは、配合する人、それを作る人、評価する人が分かれていて、データの管理が非常に煩雑で、必要なデータを集めるだけでも、多大な工数がかかり大変でした(データ解析側の自分も、データ転記ミスとか、欠損データがありすぎて大変)。それを上記開発品に絞っての話ですが、データの転記をプログラムで自動化して、一か所に集めました(これはエクセルベースなので、DBというよりかはDBの要素ですね)。ただ、それによって、転記そのものの時間がいらなくなったり、ミスのチェックが不要になるという現場側の恩恵があったこと、MI側も、一か所に集められたデータを活用して、信頼性の高いデータを活用して、機械学習モデルを構築することが出来ました。
皆様、いかがでしたでしょうか。
新明氏の講演本編では、「MIによる素材・材料開発の進化と成果創出へのアプローチ」をテーマに、MIの導入から具体的な活用事例、そして成果創出のための組織的な仕組み作りまで、包括的な取り組みを分かりやすく示していただいています。
下記の記事も併せて、ぜひご覧ください。