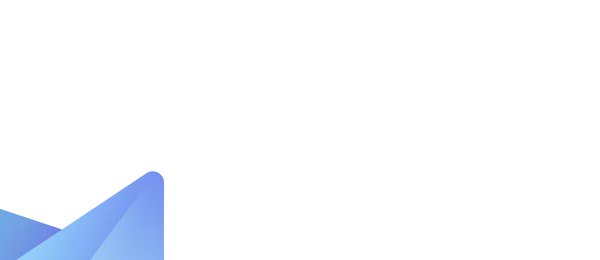近年、研究開発DXの導入・推進はますます加速し、単なる試験的導入を超え、組織レベルでの定着と拡張 にシフトしています。マテリアルズ・インフォマティクス(MI)やデータ活用を起点とした変革の波は、企業・アカデミアを横断しながら広がりを見せており、業界全体の競争力を左右する要素となりつつあります。
MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催し、過去最多となる1,800名以上の方々にお申し込みいただきました。
コスモ石油ルブリカンツ株式会社 貝戸氏のご講演では、MI推進の背景、具体的な活用事例、活動により得られた知見、そして、今後の展望について詳細にご紹介いただきました。
本記事では、参加者の方から積極的に頂いた多数のご質問に対して、貝戸氏から開催後にご回答いただいた内容をご紹介いたします。

貝戸 信博
Nobuhiro Kaito
コスモ石油ルブリカンツ株式会社技術部 次世代事業開発グループ
2010年東京理科大学大学院理学研究科化学専攻修了、同年コスモ石油株式会社に入社、コスモ石油ルブリカンツ株式会社に出向。入社してからの4年間はバイオマスの熱分解技術や磁気粘性流体の開発など、石油会社に在籍しながら非石油系の研究開発業務に従事。その後、新規需要家開拓(2年)、放熱材の営業(2年)、工業潤滑油の研究開発(1年)、潤滑油の販売管理(1年)と、短期間の人事異動で様々な業務を経験。2020年からコロナ禍での特約店向け潤滑油法人営業を経て2024年より現職、次世代事業の創出と研究開発におけるMI活用推進に従事している。
データ収集・前処理・管理について
データをフォーマット化しても実験者が入力を面倒に感じてしまい、狙い通りデータが蓄積されないということはありましたか?また、そのような場合にフォーマットを利用してもらうような工夫はされましたか?
定型フォーマットの導入を検討してみましたが、研究員の使いやすさとmiHub®にインプットするための使い勝手を両立するのは難しく、実運用には至っておりません。ただし、「セル結合の禁止」や「数値以外入力不可」など、MI活用する上での必要最低限のルールを決めるようにしています。
昔のデータを持ち出してくると実験条件が実験時期によって異なっていて使えない、使いにくいという事がしばしばあると思っているのですが、御社ではいかがでしょうか。また、あった場合はどういった対応をしているでしょうか。
実験者や時期によって差が出やすいという実験項目はございます。その場合、蓄積データ数を増やしても予測精度は上がりづらくなりますが、ある程度の実験結果の傾向を把握することは可能です。予測精度が上がりづらいことを認識し、「そういうものだ」とわかった上で、使いこなすことが重要だと考えます。
MI導入・推進体制について
貴社でも計算科学・情報科学部隊があるかと思いますが、MI-6のmiHub®を導入したきっかけはどういったものでしょうか?
弊社では、研究員とは別の計算科学・情報科学部隊を設けておりません。実験内容を理解している研究員がMIを使いこなすことを目指しており、「研究員=MIユーザー」という体制をとっております。miHub®を導入した理由は、ノーコードで使用でき、研究員に扱いやすいという理由からです。
MI解析について
ガスエンジン油の実験推奨点の検証のところで2点×3回のあとは人の手による処方調整をされたということでしたが、実験推奨点でサイクル数を増やすのではなく人の手を活用した理由はありますでしょうか?結局は人の力が必要なのでしょうか?
目標性能をすべて満たす商品を開発するために、初期段階の広い範囲からの絞り込みはmiHub®で行い、最終段階では研究員の知見で微調整するというケースが多いと考えます。すべてMIに頼った場合でもいずれ目標にたどり着くと思われますが、最後の微調整は過去の知見をもとに行った方が効率がいいと思われるため、そのようにしております。
皆様、いかがでしたでしょうか。
貝戸氏の講演本編では、「潤滑油の商品開発におけるMI活用」をテーマに、ガスエンジン油、放熱剤の開発にMIを適用した具体的な事例を交えながら、MI推進の取り組みをご紹介いただきました。活動から得られた知見や将来展望についてもお話しいただき、材料開発に携わる方にとって非常に示唆に富む内容となっております。
講演の概要記事についても、ぜひご覧ください。