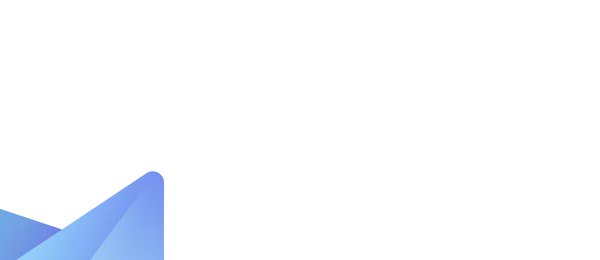MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催いたしました。
多くのセッションで参加者の方から積極的にご質問いただきました。
当日すべてに回答できなかったことから、本記事では、北陸先端科学技術大学院大学 本郷氏から開催後にご回答いただいた内容をご紹介いたします。

本郷 研太
Kenta Hongo
北陸先端科学技術大学院大学情報社会基盤研究センター 准教授
2005年に東北大学大学院工学研究科で博士(工学)を取得した後、東北大学金属材料研究所、北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、ハーバード大学(海外学振)、統計数理研究所を経て、2012年にJAIST情報科学研究科の助教として着任、2017年には准教授へ昇進し、情報社会基盤研究センターにてスーパーコンピュータ施設の管理も担当している。研究分野は第一原理量子モンテカルロ法を活用した計算材料科学およびマテリアルズ・インフォマティクスに従事している。物質科学における基礎研究のみならず、企業との産学連携研究にも従事している。
第一原理計算手法とMI研究への応用について
MO法、DFT法、QMC法など第一原理計算手法の使い分けや、MI研究で複数の手法を効果的に組み合わせる方向性についてご教示いただけますと幸いです。
第一原理計算の使い分けは、計算コスト、すなわち電子数 N に対するスケーリングの観点から考えると良いかと思います。DFT法は N3程度、高精度なMO法は N6-7程度の計算量が必要です。したがってMO法は、小分子系を対象に分光実験との定量比較を行う場合に有効です。一方、DFT法は計算コストが低く、分子から固体まで幅広く適用可能で、定性的にも定量的にも満足できる結果が得られることが多いです。ただし、分散力や磁性などではDFT法が定性的にも誤ることがあります。その場合、MO法はコスト的に適用が難しいため、代替としてQMC法を利用することがあります。QMC法はスケーリングが N3-4 程度で比較的大きな系を扱えますが、化学精度を満たすには大量の統計サンプリングが必要となり、計算資源を多く消費します。
MI研究で複数の手法を組み合わせる場合には、大量のDFTデータでモデルを構築し、少数の高精度MOデータで転移学習を行う、といったアプローチが典型的です。
電子間相互作用が大きくない系では、DFT計算が良い結果を示し、また最近ではQSGWやDMFTなどDFT計算の枠組みを拡張して電子間相互作用をよりまじめに考慮する手法が提案されていると認識しています。これらのpost-DFT的な手法と比較した、Q(D)MCの長所はございますでしょうか。
GWやDMFTはグリーン関数法に基づき、励起状態やスペクトルの定量評価に用いられます。一方、QMC法は基本的に基底状態を扱う手法で(励起状態も原理的には可能ですが計算コストが高い)、例えば異なる磁気秩序の安定性を比較する場合に有効です。したがって、目的に応じて使い分けるのが適切と考えます。
量子力学の計算は高精度ながら計算時間・限られた計算資源がハイスループット実験まで展開していくうえで解消したい課題になります。その場合、限られた資源の中で、高精度な計算をどのように活用していけばよいか、ご教示いただけますでしょうか。
高精度計算で得られるデータには限りがありますので、少数の高精度データを転移学習などに用いるのが典型的な活用法です。
第一原理計算は非常に強力なアプローチだと思いますが、どのような材料系や特性の予測において、特にその力を発揮するとお考えでしょうか。また、このアプローチの課題部分についてもご教示いただけますと幸いです。
第一原理計算は量子力学に基づくため原理的にはあらゆる物質に適用可能で、その汎用性が強みです。ただし、近似の導入によって対象や物性に向き不向きが生じます。また計算コストの制約から、孤立分子や結晶のような理想化系が主な対象となり、実材料をそのまま扱うことはできません。そのため、実材料と理想系をつなぐ「モデリング」の工夫が重要となり、ここが第一原理計算を材料科学に応用する際の核心部分となります。
同じような高精度第一原理計算の方法は、世界中のどこかの研究者が検討されていて、デッドヒートで競い合っているか、もしくはニッチでしょうか?
QMC法に限って言えば、米国の国立研究所や欧州の一部グループで盛んに研究されており、研究者人口としてはニッチな分野に属します。ただし、近年は中国でもQMC関連の研究を進めるグループが確認されています。
機械学習ポテンシャルと構造生成について
汎用機械学習ポテンシャル(uMLIP)に関する、先生のご知見をお伺いできませんでしょうか?
「ノーフリーランチ定理」が示すように、万能の機械学習モデルは存在しません。汎用MLポテンシャルも万能ではありませんが、多くの問題で高精度かつ高速な計算を実現しており、実務上は極めて有用です。私自身も結晶構造探索などに活用しています。ただし、どのようなデータで構築されたかを常に意識し、その適用限界を理解することが重要です。
拡散モデルは原理的にMDとは相性が良さそうですが、量子化学分野でも同じように注目されているのでしょうか?アーキテクチャとして、より注目されているものがあれば伺いたいです。
新規化合物探索の観点から注目されています。候補分子に対して振動数解析を行い安定性を確認した上で電子物性を計算することで、信頼性の高い探索が可能です。最近ではグラフ表現を用いた拡散モデルや、言語モデルと組み合わせたマルチモーダル生成モデルも提案されています。
「結晶構造探索」とは、何らか物性値が良い構造を探索するのではなく、そもそも物理的に成立する(新規な)構造を探索するということでしょうか?
その通りです。講演では、与えられた組成に対して形成される結晶構造そのものを最適化問題として探索する手法を紹介しました。
計算リソースと企業での運用について
実際にシミュレーションを企業の事業部内で運用するとなると、スパコン設備は必要不可欠になってしまうのでしょうか?
必ずしもスパコンが必須ではなく、オンプレミス導入、レンタル・リース、クラウドなど複数の選択肢があります。クラウドは外部にデータを置く制約がありますが、計算内容と必要資源が見積もれる場合には有効な選択肢となります。
企業視点からすると、スパコンを使った計算に手を出すこと自体にハードルの高さを感じてしまいます。企業独自で人材育成や技術検討を行うより、大学や研究機関の協力を得るのが現実的なアプローチでしょうか?
例えば社会人ドクター制度は、人材育成と産学連携を両立できる仕組みであり、本学でも「産学連携社会人コース」を設けています。遠隔で講義や研究指導を受けながら最短1年で学位取得が可能です。
皆様、いかがでしたでしょうか。
本郷氏の講演本編では、「次世代MIのための高精度第一原理計算」をテーマに、MI研究の現状と展望について、JAISTの保有するスーパーコンピュータを活用した成果事例を交えながら、詳細に解説いただいています。
講演概要記事も併せて、ぜひご覧ください。