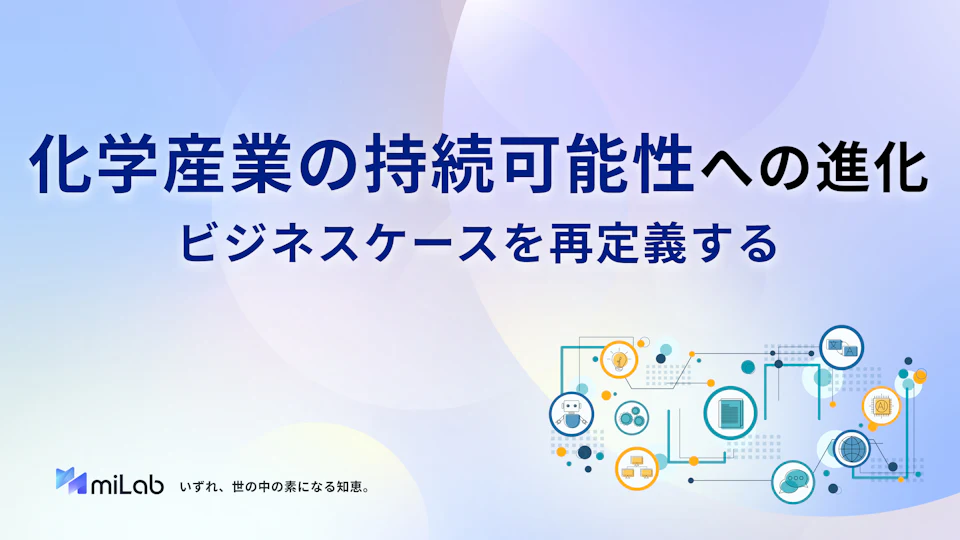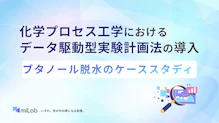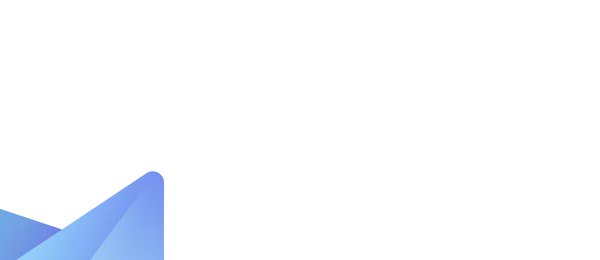序論:持続可能性という新しい挑戦
化学産業は、人類の発展を支えてきた中核的な産業であると同時に、資源利用や環境影響と深く結びついています。今、この産業は「従来型のビジネス慣行」と「地球規模の持続可能性課題」という二つの要請をどう調和させるか、転換点に立っています。
この挑戦は単に技術開発だけでなく、企業の価値観や意思決定のあり方を問い直すものです。Laszlo(2003)が論じた「ビジネスの進化」は、この転換を理解するうえで示唆を与えます。アインシュタインの言葉を借りれば、問題を生んだときと同じ思考では解決できません。持続可能性の実現には、技術や方法論だけでなく、ビジネスの倫理やパラダイムそのものを再考することが求められています。
ビジネスのパラダイムとその影響
産業革命以降、収益性は大きく高まり、ビジネスは社会の制度や文化に影響を及ぼす基盤となりました。この過程で広がったのは、以下のようなモデルです。
- 適者生存:「生き残りの尺度は利益」という競争的思考
- 戦争としてのビジネス:市場を戦場に見立てた支配と利益の追求
- 機械的組織運営:組織を効率追求の機械とみなし、人間的側面を従属させる
これらは確かに効率やスケールの拡大に寄与しました。しかし同時に、「単一の利益指標への集中」によって、社会・環境・人材といった多様な価値を後景に追いやる傾向をもたらしました。結果として、成長は得られても環境破壊や格差拡大といった副作用も表面化してきました。

図1. 現代ビジネス組織における利益追求パラダイムのイメージ
サステナビリティ概念の登場
こうした背景から、利益追求型の成長は次第に疑問を持たれるようになりました。環境・社会・健康に複合的な影響を与えていることが認識されたからです。
サステナビリティは、その応答として登場しました。その目的は、
- 生態系の保全と責任ある資源利用
- 経済的・社会的公正の実現
- 人間の自己実現への健全な道筋の提供
を統合的に目指すことにあります。つまり、サステナビリティは制約条件だけではなく、新しい成長の方向性を指し示すものです。
ビジネス啓蒙への移行
持続可能性を前提とした新しいパラダイムでは、収益性は放棄されるのではなく、社会的・環境的価値と両立させる形で再定義されます。
- 「有機体モデル」として、組織は生態系や文化的環境の変化に応じて戦略を調整し、未来へ適応する。
- エコセントリックな倫理に基づき、win–winの解決策を探る。
化学産業の持続可能性を考える際には、評価の対象を単一の工場の効率性に限定せず、企業、地域生態系、経済、さらに地球規模の影響へと拡張していく必要があります(図2)。図は、化学プラントを出発点とし、そこから同心円状に広がる多層的な関心領域を示しています。この枠組みは、持続可能性が部分最適ではなく全体最適を志向することを視覚的に表しています。
こうした全体最適を志向するパラダイムにおいては、理念と実装をどう結びつけるかが課題となります。ここで重要なのは、利益と持続可能性の両立可能な解をデザインすることです。その実現に向けて、近年のデジタル手段──たとえばマテリアルズ・インフォマティクス(MI)やラボオートメーション(LA)など、以下では「デジタル基盤」と呼びます──は、複雑な利害や制約を調和させる実践的な基盤を提供しつつあります。

図2. 化学産業における持続可能性の多層的パラダイム
化学産業における持続可能性課題の特徴
持続可能性は化学産業に独自の課題を突きつけます。それは単なる「工場単位の効率化」にとどまらず、システム全体の捉え直しを迫るものです。製品やプロセスの環境影響を縮減するだけでなく、サプライチェーン全体や社会への波及効果を考慮する必要があります。
動的な理解の必要性
持続可能性は固定的な目標ではなく、社会的・技術的状況の変化に応じて進化する概念です。化学産業は、経済・社会・環境の三要素を統合的に満たす製品やプロセスを提供しつつ、規制や市場の変動、技術進展に即応できる柔軟性が求められます。
こうした柔軟性を確保するためには、将来シナリオを比較・評価し、複雑な要因を踏まえた意思決定を行う仕組みが欠かせません。ここで役立つのがデータ駆動型の手段です。たとえばインフォマティクスにより多様なデータを基盤にシナリオ分析や需要予測を可能にし、ラボオートメーションによる再現性の高い実験を通じて、環境変化に応じた適応策を迅速に検証することを支援します。
システム境界の拡張
化学産業が持続可能性を実現するためには、評価の枠組みを単一の工場内の効率性に限定せず、サプライチェーン全体から製品ライフサイクル全体へと広げて考える必要があります。「どの段階を評価対象とするか」と「どのスコープで統合的に捉えるか」をそれぞれ考えてみましょう。
評価の段階(ライフサイクル上の要素)
- 原料調達(例:バイオマス利用や土地利用変化)
- 製造プロセス(エネルギー効率、副産物利用など)
- 流通・使用段階(製品寿命、安全性など)
- 廃棄・リサイクル(循環型設計の有無)
分析のスコープ(3層の広がり)
- 工場レベル:エネルギー投入量、副産物削減、設備稼働効率といった工場内の改善
- サプライチェーンレベル:原料調達から物流、流通に至るまでの排出や社会的コストを含めた評価
- ライフサイクル全体:使用段階の安全性や長寿命化、廃棄・リサイクルまで含めた全体的な影響の把握
こうした多層的な視点を統合するうえで、デジタル基盤が重要です。MIは原料から廃棄まで各段階で発生するデータを共通の基盤に統合し、数理的に最適化の余地を示します。LAは実験・計測を効率化して再現性の高いデータを提供し、統合分析の信頼性を高めます。結果として、工場からサプライチェーン、さらにライフサイクル全体へと広がる評価の枠組みをデータで結びつけ、持続可能性の「部分最適」ではなく「全体最適」を目指すことが、次世代の化学産業に求められます。
社会・経済的側面の評価
経済性は持続可能性評価の中で最も進展している分野ですが、課題も残されています。例えばLCA(ライフサイクルアセスメント)と経済モデルを統合し、意思決定のマクロ的影響を評価する仕組みはまだ途上です。
一方、社会的次元においてはCSRやESGの活動が進んでいますが、科学・工学と社会的影響をどう結びつけるかは難題です。たとえば新素材の開発が、雇用創出・地域コミュニティ・健康への影響とどう接続するかを明確にする必要があります。
デジタル基盤はここで、工学データと社会的データの接点を可視化し、意思決定者にとって「見えない価値」を見える化する役割を果たし得ます。
Planetary Boundaries(地球の限界)との整合
Rockströmらが提唱した「Planetary Boundaries」フレームワークは、人類活動が安全に存続できる環境の限界を定義するものです。化学産業はこれらの境界と密接に関わっています(図3)。
- 気候変動:GHG(CO₂・N₂O)削減への貢献
- 海洋酸性化:排出抑制による海洋生態系の保護
- 窒素・リン循環:肥料・化学品由来の流出管理
- 淡水利用:供給網全体での水効率化
- 新規化学物質:プラスチックや未規制物質によるリスク低減
これらの境界を尊重することは、倫理的責務であると同時に、将来市場にアクセスするための前提条件でもあります。
では実際に、どのようにして境界を守りつつ産業活動を行うのか。 そのためには、排出量や資源利用を正確に把握し、将来の影響を予測しながら意思決定に反映する仕組みが不可欠です。ここでも、インフォマティクス技術を活用することで、境界を超えないための科学的根拠と社会・産業による実装能力の橋渡しを可能にします。

図3. 9つのPlanetary Boundariesと化学産業の関与領域
規制と資源制約への対応
さらに化学産業は、以下のような課題に直面しています。
- 制約された資源条件の下での生産ルート再設計
- 国際規制・条約(例:REACH、CSRD)への適合
- 健康と環境に安全な化学物質の開発と確保
規制遵守や効率改善の先を見越した設計と全体最適化を必要とします。規制はしばしば動的に強化され、資源条件も変動するため、固定的なルール順守だけでは対応しきれません。むしろ「将来のリスクを予測し、事前にシナリオを組み込むこと」が競争力の条件となります。
このときにデジタル基盤がどう活用されるのか。設計段階から規制要件や資源条件をモデルに組み込み、リスクや制約を可視化してシナリオを比較できれば、後手のコンプライアンス対応ではなく、先手を打ったイノベーションへと転換できます。こうした基盤が、化学産業を駆動し、市場アクセスを中長期的に支えることになります。
持続可能性に取り組むことの意義と機会
化学産業が持続可能性の課題に挑むことは、単なる規制対応やコスト増の負担ではなく、新しい機会の創出につながります。むしろ、課題を先取りする姿勢こそが、企業の競争力と信頼を高める源泉となります。
ここで重要なのは「持続可能性=制約」という発想から、「持続可能性=イノベーションの駆動力」という認識への転換です。その実現において、デジタル基盤は、探索の加速・不確かさの管理・データの資産化を可能にするツールとなります。
エコ効率性の向上と利益創出
資源効率やエネルギー効率を高めることは、環境負荷を下げると同時にコスト削減をもたらします。
- MIによる最適化:少ない試行で歩留まり改善や副産物削減の条件を導出
- LAによる自律実験:省エネ設計や連続プロセス条件を効率的に探索
結果として、「環境負荷の低減=収益改善」という両立を実現できます。
新市場への拡大
未充足の社会的・環境的ニーズに対応することは、新しい市場開拓につながります。
- バイオ由来化学品、リサイクル可能材料、グリーン水素など
- 医療・農業・エネルギーなど社会課題に直結する分野
MIは膨大な候補材料を短時間でスクリーニングし、事業化に足る性能・安全性・LCA適合性を備えたものを抽出する力を持っています。
双方に利益をもたらすイノベーション
サステナビリティを前提にした設計は、win–winの解決策を導きます。
- 高性能ポリマーを開発しつつ、循環性を確保する
- 農業用化学品の効果を高めつつ、環境残留を抑える
- 電池材料で高性能化とリサイクル性を両立させる
これらは従来なら「トレードオフ」とされていた領域です。MIの多目的最適化やシミュレーション連携は、折衷ではなく新しい最適点を提示します。
規制強化下でのコア競争力の獲得
今後、資源・環境規制はさらに強化されることが予想されます。この環境下で必要なのは、規制を順守する力だけでなく、むしろ先回りして適合する力です。
- 研究段階から規制条件をモデルに組み込む
- 社会的要請をKPIに反映させる
- データに基づく透明性を確保し、説明責任を果たす
これにより「コンプライアンス対応企業」ではなく、「規制を牽引するリーダー」としての地位を築くことができます。
ステークホルダーへの価値提供
地域社会、政策立案者、顧客など多様なステークホルダーに対して、持続可能性の成果を見える化し、共有することは戦略的な優位性を生みます。
- LCAや排出量の透明な報告
- 地域資源の循環に貢献する仕組みづくり
- 社会的信頼の蓄積によるブランド価値向上
ここでもMIは、複雑なデータを分かりやすく示す可視化基盤として機能します。
さらなる展望
こうした取り組みは、さらに次の波及効果を生みます。
- 政策形成への貢献:産業データから得られる知見を政策や国際ルールづくりに還元
- 社会的信頼の維持:透明な業務運営と規制適合により社会的信頼を確保
- 倫理の昇華:単なる利益追求を超え、地球規模課題の解決に資する企業像へ
この流れは、健全なビジネス合理性と倫理的意義の両方を兼ね備えています。
結論と研究者への示唆
化学産業が持続可能性へと進化することは容易ではありません。確立されたビジネスモデル、そして膨大な社会・経済・技術・環境課題が立ちはだかります。しかし、その挑戦から得られる報酬は、事業の合理性と社会的正当性を同時に満たすものです。
研究者やエンジニアにとっては、これは意思決定プロセスの再設計を意味します。材料・プロセス開発において、性能・コストだけでなく、環境・社会的な指標を統合的に扱う力が求められます。MIやLAはそれを支える可能性を大きく秘めており、各側面で活用事例が増加しています。
参考文献
- Laszlo, K. The Evolution of Business: Learning, Innovation, and Sustainability in the Twenty-First Century. World Futures 2003, 59 (8), 605–614. https://doi.org/10.1080/713747097.
- Bakshi, B. R.; Fiksel, J. The Quest for Sustainability: Challenges for Process Systems Engineering. AIChE Journal 2003, 49 (6), 1350–1358. https://doi.org/10.1002/aic.690490602.
- Richardson, K.; Steffen, W.; Lucht, W.; Bendtsen, J.; Cornell, S.; Donges, J. F.; Drüke, M.; Fetzer, I.; Bala, G.; von Bloh, W.; Feulner, G.; Fiedler, S.; Gerten, D.; Gleeson, T.; Hofmann, M.; Huiskamp, W.; Kummu, M.; Mohan, C.; Bravo, D.; Petri, S. Earth beyond Six of Nine Planetary Boundaries. Science Advances 2023, 9 (37). https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458.
- Meng, F.; Wagner, A.; Kremer, A. B.; Kanazawa, D.; Leung, J. J.; Goult, P.; Guan, M.; Herrmann, S.; Speelman, E.; Sauter, P.; Lingeswaran, S.; Stuchtey, M. M.; Hansen, K.; Masanet, E.; Serrenho, A. C.; Ishii, N.; Kikuchi, Y.; Cullen, J. M. Planet-Compatible Pathways for Transitioning the Chemical Industry. Proceedings of the National Academy of Sciences 2023, 120 (8). https://doi.org/10.1073/pnas.2218294120.
- Matlin, S. A.; Cornell, S. E.; Krief, A.; Hopf, H.; Mehta, G. Chemistry Must Respond to the Crisis of Transgression of Planetary Boundaries. Chemical Science 2022, 13 (40), 11710–11720. https://doi.org/10.1039/d2sc03603g.