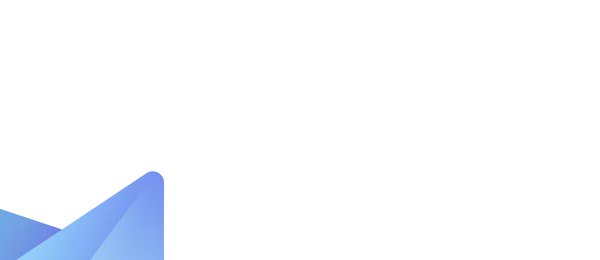MI-6株式会社では、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)に特化したカンファレンス「MI Conf 2025 - Materials Informatics Conference -」(以下、MI Conf 2025)を2025年7月16日に開催いたしました。
多くのセッションで参加者の方から積極的にご質問いただきました。
当日すべてに回答できなかったことから、本記事では、JFEスチール株式会社 須藤様から開催後にご回答いただいた内容をご紹介いたします。

須藤 幹人
Mikito Suto
JFEスチール株式会社スチール研究所サステナブルマテリアル研究部 グループリーダー
2009年筑波大学大学院数理物質科学研究科化学専攻修了、同年、JFEスチール株式会社に入社。スチール研究所にて飲料缶や食缶向け鋼板の開発に従事。その後、2017年に新設された機能材料研究部(現サステナブルマテリアル研究部)に異動。機能素材開発ではマテリアルズ・インフォマティクスやロボット実験などを社外との協業を通じて積極的に活用中。
ロボット・自律実験システムについて
恐らく様々な材料開発の検討PJをお持ちだと思うのですが、今回御紹介頂いたテーマにMI自律実験を適用する事を決めた経緯や背景など教えて頂ければ幸いです。事前にこのテーマはマッチしそうだ、など決断における勘所があればぜひご教授いただきたく存じます。
向上させたい特性を自律実験システムで自動的に評価できるか、できない場合は、特性向上に寄与する物性を評価できるかがまずは重要です。その次に特性に作用しそうな作製パラメータを自動で変更できるかです。
材料スクリーニングと発見された物質について
材料スクリーニングのフローは一般的なものなのでしょうか?例えば無機化合物と有機化合物でフローが大きく異なるなどもあるのでしょうか?
どのような特性を向上させたいか、その物質がどのような環境(デバイス)で使われるか等でスクリーニングフローは異なってきます。このフロー構築が人の腕の見せ所と思います。
MI/PIとシミュレーションについて
紹介された材料に関し、イオン伝導度がMDシミュレーションより3桁オーダーで上回る測定結果が出た、という話がありましたが、逆にMDで抜けていた要素は何だったのでしょうか。 P16にてMDから計算されたイオン電導度と実験結果から計算されたイオン電導度の値がかなり違うように感じました。理論値と実験値の数値誤差についてはどのように解釈されたのかお聞きしたいです。
作製した膜をTEM等で詳細に解析したところ、MDのモデルより大きなスケールで構造に特徴がありました。この構造の影響でイオン伝導度が向上したと現在は考えております。
皆様、いかがでしたでしょうか。
須藤氏の講演本編では、「素材開発グループにおけるMIやロボット実験活用」をテーマに、MI、計算科学そしてロボティクスを駆使して素材開発の速度と網羅性を飛躍的に高める取り組みの内容に加え、実プロセス適用時の課題まで率直に示していただいています。
下記の記事も併せて、ぜひご覧ください。